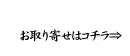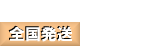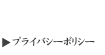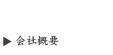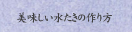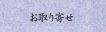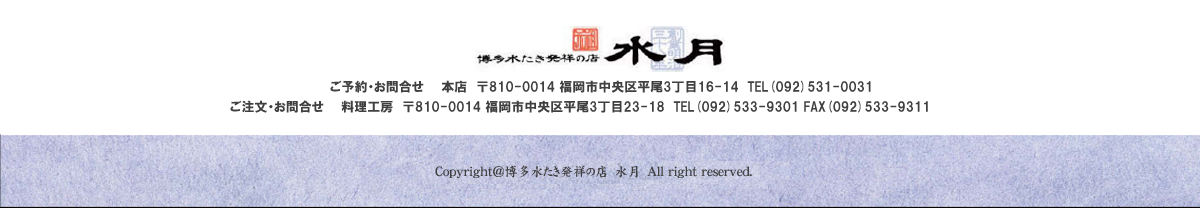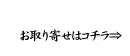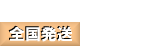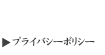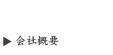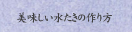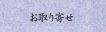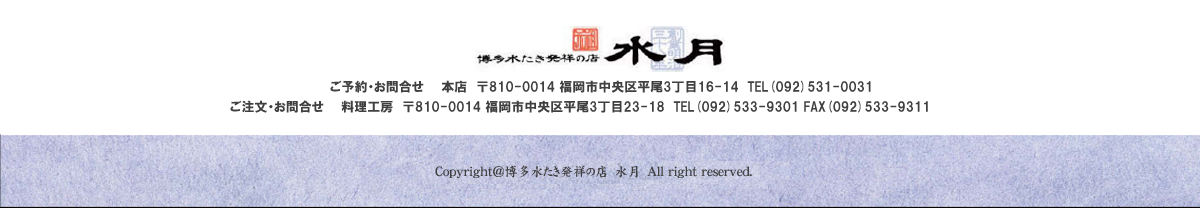水月の歩み、それは
「博多水たき」の発祥と軌跡。
後に水月の初代料理長となる林田平三郎は長崎生まれ。
まだ日本では外国文化の色もうすい明治30年、15歳で単身香港に渡り英国人の家庭に住み込む。
西洋と中華の世界二大食文化を前に、平三郎は調理法の習得に日々明け暮れていた。
ある日、西洋料理の「コンソメ」と中華料理の「鶏を炊き込む」という西・中の”スープ料理”をなんとか日本風にアレンジできないものか、平三郎は考えた。
帰国後、さっそくその技法をミックスさせ、博多人の口にもっとも合う味を試行錯誤した。
そんな中、仕入れたニワトリの足の裏に硬さの違いを知り、山奥の硬い地面で育った鶏と海岸の砂地で育った鶏を一緒に料理しては、肉の柔らかさにムラが出来ることに気付く。
そこで鶏は九州の鶏の雄だけに限定した。戦前は貨車で取り寄せ「水たき列車」とも呼ばれていたそうだ。
”これ”という味に出会えるまで様々な紆余曲折を経、平三郎はついに明治38(1905)年、「博多水たき」の味を編み出した。
博多の土手町(須崎)にオープンさせた念願の店の前には、朝8時の開店と同時に行列ができ、博多の人々の口に広く喜ばれていたことをうかがわせる。
当時開催されていた世界博に訪れていた日本全国の食通を唸らせたことが、水たきを博多の新名物としてその名を決定的にしたのでは、と三代目は語る。
あれから110余年―。水月の味は今も尚、あの頃の味を守り続け、変わらぬ味をお客様にご提供している。
「水月」の水たきは博多に産声をあげ、今では博多を代表する、博多の味。
「水月」はその名に恥ずことなくこれからも初代の味を守り続けていく。
それは初代の味こそ日本一の味、「水月」の味、という自信に一点の曇りもないことの証である。
|